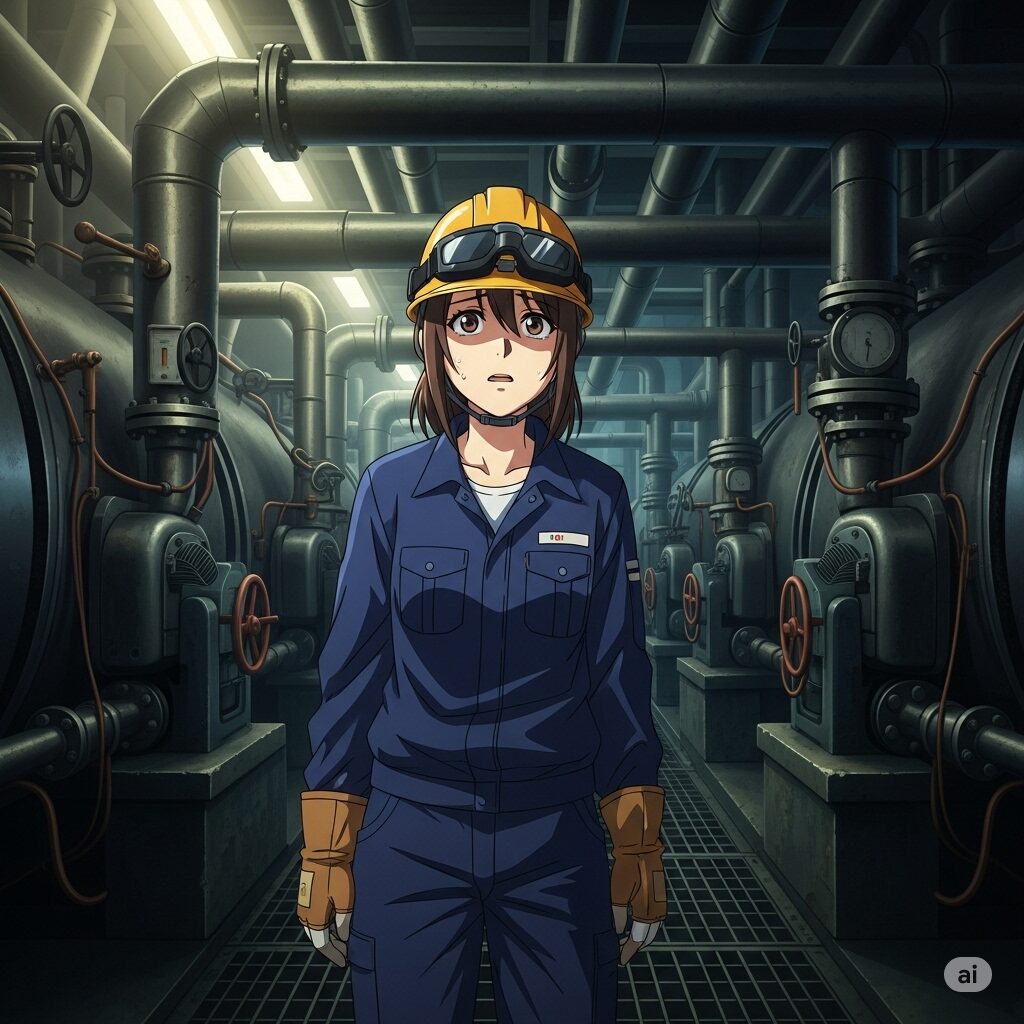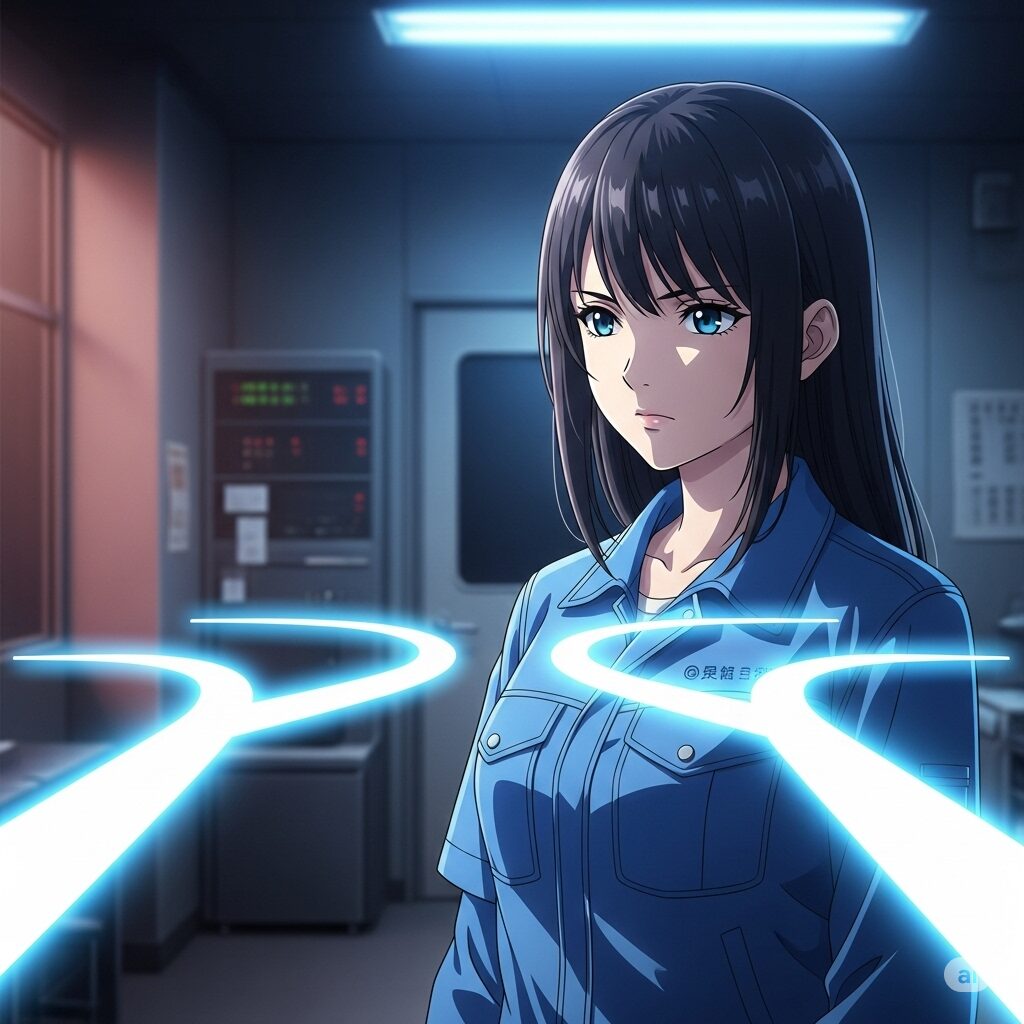【給料安い?】ビルメン歴20年の俺が語る「仕事きつい・離職率高い」の残酷な真実と、それでもこの業界で飯を食っていく方法

「ビルメンの仕事って、実際どうなの?」「きついって聞くけど、将来性はある?」。そんな疑問や不安を抱えていませんか。ネットには様々な情報が溢れていますが、現場のリアルな声は少ないもの。この記事では、ビルメンテナンス業界に20年以上身を置く私が、離職率の本当の理由、そして「きつい」と言われる現場でたくましく生き抜き、キャリアを築くための具体的な方法を本音で語ります。この記事を読めば、あなたのビルメンに対する見方が180度変わるかもしれません。
- なぜビルメンは「きつい」と言われるのか?ベテランが明かす5つの根本原因
- 離職率20%超えは本当?若手がすぐ辞める職場の共通点
- 【自己診断】あなたはビルメンに向いている?後悔しないための適性チェック
- 給料UPと安定を掴む!現場で重宝される人材になるための具体的アクションプラン
- 5年後、10年後も食いっぱぐれない!ビルメン業界の将来性とキャリアパス
1. なぜビルメンは「きつい」と言われるのか?ベテランが明かす5つの根本原因
俺がこの業界に足を踏み入れた20年前から、「ビルメンはきつい」という言葉は常に付きまとってきた。だが、その「きつさ」は単なる肉体労働だけを指すものじゃない。本当の原因は、もっと根深いところにあるんだ。
第一に、精神的なプレッシャー。トラブルは待ってくれない。商業施設なら営業中に、オフィスビルなら業務中に、突如として起こる漏水や空調停止。利用者からのクレーム、オーナーからのプレッシャーを一身に受けながら、冷静に、そして迅速に対応しなければならない。この重圧は経験の浅い者にはかなりこたえるはずだ。
第二に、不規則な勤務体系。24時間365日、ビルは生きている。当然、俺たちの仕事にカレンダーは関係ない。泊まり勤務(宿直)や、世間が休んでいるゴールデンウィーク、年末年始の出勤も当たり前。友人や家族と予定を合わせにくいのは、若い奴らには特にきついだろう。
第三に、覚えることの多さ。電気、空調、給排水、消防設備…と、ビル一つを管理するには膨大な知識と技術が求められる。「ビルメンは楽」なんて言う奴もいるが、それは最低限の仕事しかしていないから。本当にプロとして飯を食っていくなら、常に学び続ける姿勢が不可欠だ。
第四に、正当に評価されにくい環境。トラブルを未然に防ぎ、何も起こらない「当たり前」を維持するのが俺たちの仕事。だが、何事もなければ評価されず、トラブルが起きた時だけ矢面に立たされる。このやりがいの見えにくさが、モチベーションを削いでいくんだ。
最後に、人間関係の複雑さ。現場には様々な年代、経歴の人間がいる。昔気質の職人もいれば、プライドだけ高い年配者もいる。オーナー、テナント、協力会社との折衝も重要で、技術だけでなく高いコミュニケーション能力が求められるんだよ。
2. 離職率20%超えは本当?若手がすぐ辞める職場の共通点
厚生労働省の調査でも、ビルメンテナンスが含まれる「サービス業」の離職率が高いのは事実だ。俺の経験から言っても、入社して3年以内に半分近くが辞めていく職場なんてザラにあった。そうした「若手が根付かない職場」には、いくつかの明確な共通点がある。
まず、「見て覚えろ」という古い教育体制。今の時代にこれは通用しない。体系的な研修やマニュアルがなく、先輩の背中だけを見て仕事を覚えろというのは無責任すぎる。質問しにくい雰囲気も相まって、新人は孤独感を深めて辞めていく。
次に、給与の低さと昇給の不透明さ。未経験からでも入れる業界だからこそ、初任給が低いのは仕方ない面もある。だが、資格を取っても手当が雀の涙だったり、何年働いても昇給が見込めなかったりする会社はダメだ。「頑張っても無駄」だと感じさせたら、優秀な人材ほど早く見切りをつけてしまう。
そして、現場の設備の古さ。いわゆる「ハズレ現場」ってやつだ。老朽化した設備は当然、故障やトラブルが頻発する。その度に場当たり的な修理を繰り返し、根本的な改修には費用を出さない。そんな現場に配属されれば、心身ともにすり減っていくのは目に見えている。結局、将来性のない会社、現場からは人が離れていくのさ。
3. 【自己診断】あなたはビルメンに向いている?後悔しないための適性チェック
この仕事は、誰にでも務まるわけじゃない。もし、ビルメンへの転職を考えているなら、以下の項目で自分をチェックしてみてほしい。
- 知的好奇心があるか?:設備の仕組みや新しい技術に興味を持てるか。
- 地味な作業をコツコツ続けられるか?:点検や清掃など、ルーティンワークを疎かにしないか。
- 冷静沈着でいられるか?:緊急時にもパニックにならず、やるべき事を考えられるか。
- 人と話すのが苦じゃないか?:オーナーや業者と円滑なコミュニケーションが取れるか。
- 体力に自信があるか?:不規則な勤務や、時には力仕事にも対応できるか。
3つ以上当てはまるなら、ビルメンとしての素質は十分にある。逆に、一つも当てはまらないなら、この業界は考え直した方がいいかもしれない。楽な仕事だと思って入ってくると、必ず痛い目を見るからな。
4. 給料UPと安定を掴む!現場で重宝される人材になるための具体的アクションプラン
「きつい」だの「給料が安い」だの言われる業界だが、やり方次第で給料を上げ、安定した地位を築くことは可能だ。20年やってきた俺が保証する。
重要なのは、**「ビルメン三種の神器」**と呼ばれる資格を足掛かりに、専門性を高めることだ。具体的には、「第二種電気工事士」「危険物取扱者乙種4類」「二級ボイラー技士」。まずはこれを取得する。話はそれからだ。
だが、資格だけじゃダメだ。本当に価値があるのは**「資格+実務経験」**だ。空調のトラブルに強い、消防設備なら任せろ、といった「自分の武器」を持つこと。そのためには、日々の業務の中で一つでも多くの経験を積み、分からないことは徹底的に調べる貪欲さが必要になる。
さらに、報告書作成能力やPCスキルも磨いておけ。現場仕事と思われがちだが、オーナーへの報告や見積もりの作成など、事務作業は意外と多い。WordやExcelが使えるだけで、他の作業員と大きく差をつけられる。これができる人間は、将来的に所長やマネージャーへの道も開けてくるんだ。
5. 5年後、10年後も食いっぱぐれない!ビルメン業界の将来性とキャリアパス
AIに仕事が奪われるなんて話もあるが、俺はビルメンの仕事はなくならないと確信している。なぜなら、現場で起きる突発的なトラブル対応や、泥臭い物理的な作業は、人間にしかできないからだ。建物がある限り、俺たちの仕事は絶対になくならない。
キャリアパスとしては、まずは現場で経験を積み、「電気主任技術者(電験三種)」や「建築物環境衛生管理技術者(ビル管)」といった上位資格の取得を目指すのが王道だ。これらの資格があれば、選べる会社の幅も、給与水準も一気に上がる。
一つの会社で所長を目指すのもいい。系列系のビルメン会社なら、親会社の正社員として厚い福利厚生を受けられる可能性もある。あるいは、高い専門性を武器に、より待遇の良い独立系の会社へ転職する「わらしべ長者」のようなキャリアアップも、この業界なら十分に可能だ。
結局、どこの業界でも同じさ。文句を言って辞めていくか、頭と体を使って自分の価値を高めていくか。この業界には、後者を選んだ人間に必ず応えてくれるだけの懐の深さがあるんだよ。
あとがき
ビルメンテナンスの仕事は、決して華やかではありません。しかし、社会のインフラを静かに支える、誇り高い仕事です。この記事が、あなたの抱える不安を少しでも解消し、この業界で一歩を踏み出す、あるいは歩み続けるための後押しになれば、これ以上嬉しいことはありません。現場のどこかで、あなたと共に仕事ができる日を楽しみにしています。