【悲報】「お祈り」されたのは俺の方だった…ビルメン採用担当が語る、心が折れた内定辞退のリアルすぎる断り文句3選
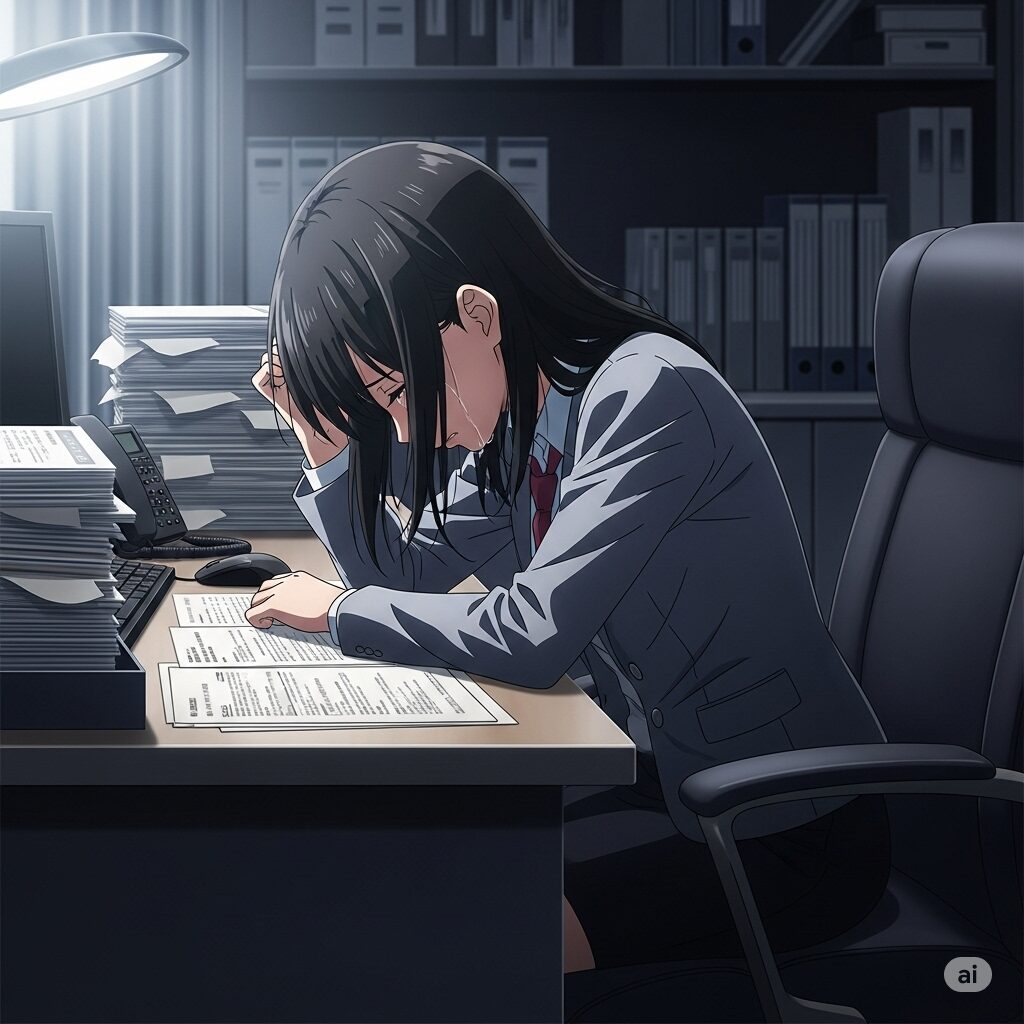
「御社の益々の発展を心よりお祈り申し上げます」…またこの一文か。手塩にかけて育てた内定者に、ある日突然フラれるのがビルメン採用担当の宿命。なぜ、あれほど「働きたい」と言ってくれた彼らは去っていくのか?この記事では、現場を知るビルメン採用を担当したこともある私が、実際に経験した(そして心が折れた)内定辞退の典型的なパターンと、その裏にある応募者の本音を暴露します。採用のミスマッチを防ぎたい同業者の方も、ビルメン業界への転職を考えている方も、ぜひご一読ください。
- 心が抉られる…「テンプレート完璧型」辞退
- むしろ清々しい?「本音ぶっちゃけ型」辞退
- 一番やめてくれ…恐怖の「サイレント」辞退
4. 本文
心が抉られる…「テンプレート完璧型」辞退
一番多いのがこのタイプですね。「貴社にご縁がなかったこと、大変残念に思います」といった、非の打ち所がない完璧な文章で辞退の連絡をくれる方々です。
面接では「御社の〇〇という設備に興味があります!」「宿直勤務も問題ありません、体力には自信があります!」と、目を輝かせて語ってくれたじゃないか…。こちらも現場のベテラン所長に頭を下げて、「いい人材がいるんです!」って紹介して、受け入れ準備まで進めていたのに。
メールの文面が丁寧であればあるほど、「あの時の熱意はどこへ…」と、人間不信になりそうになります。おそらく、もっと条件の良い他社に決まったのでしょう。それは仕方のないことですが、せめて「給与面で折り合いがつかなかった」とか、一言でも本音を漏らしてくれた方が、こちらも次への改善点が見つかるのに…と思ってしまいます。丁寧な言葉の壁が、一番心をえぐるんですよね。
むしろ清々しい?「本音ぶっちゃけ型」辞退
次に、テンプレートとは真逆の「本音ぶっちゃけ型」。これはこれで精神的にクルものがあります。
「正直に申し上げますと、提示いただいた給与では生活が厳しいです」 「実際に現場を見学させていただき、自分には務まらないと感じました」 「他社のほうが年間休日が多かったので、そちらに決めました」
など、非常にストレートに理由を伝えてくれるパターンです。言われた直後は「うっ…」と胸が痛みますが、数日経つと「正直に言ってくれてありがとう」という気持ちが芽生えてくるから不思議です。
我々ビルメン業界は、社会インフラを支える誇り高い仕事ですが、待遇面で大手メーカーなどと比べると見劣りする部分があるのも事実。そこを理解した上で、改善していくのが会社の役目です。応募者のリアルな声は、会社を良くするための貴重な意見。…そう頭では分かっていても、やっぱり面と向かって言われると、しばらくは凹みますけどね(笑)。
一番やめてくれ…恐怖の「サイレント」辞退
そして、採用担当者が最も恐れているのが、この「サイレント辞退」です。
内定承諾書を送った後、何の連絡もなし。こちらから電話をしても留守電。メールを送っても返信なし。昨日まであんなにスムーズにやり取りできていたのに、まるで神隠しにあったかのように、プッツリと連絡が途絶えてしまうのです。
「何か事件にでも巻き込まれたんじゃ…」と本気で心配になることもあります。承諾してくれるのか、辞退するのか、それだけでも教えてくれれば、こちらも次の候補者に連絡ができるのに…。会社の備品(作業着や工具)の発注を止めたり、他の応募者の方に「申し訳ありません、採用枠が埋まりました」と伝えてしまった後だったりすると、もう目も当てられません。どうか、社会人のマナーとして、一言だけでいいので連絡をくれることを切に願います。本当にお祈りしたいのはこっちの方ですよ…。
あとがき
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。採用担当の愚痴のようなブログになってしまい、申し訳ありません。ですが、これがビルメン業界の採用現場で日々起きているリアルです。キラキラした世界ではありませんが、建物の安全と快適を裏で支える、社会になくてはならない仕事だと誇りを持っています。色々ありますが、この仕事のやりがいを分かってくれる新しい仲間が来てくれることを信じて、私は明日も面接会場へ向かいます。もしどこかの現場で会ったら、気軽に声をかけてくださいね。







