【地獄か?天国か?】ビルメン歴20年のベテランが明かす、若手が根付かない5つの残酷な現実と生き残り術
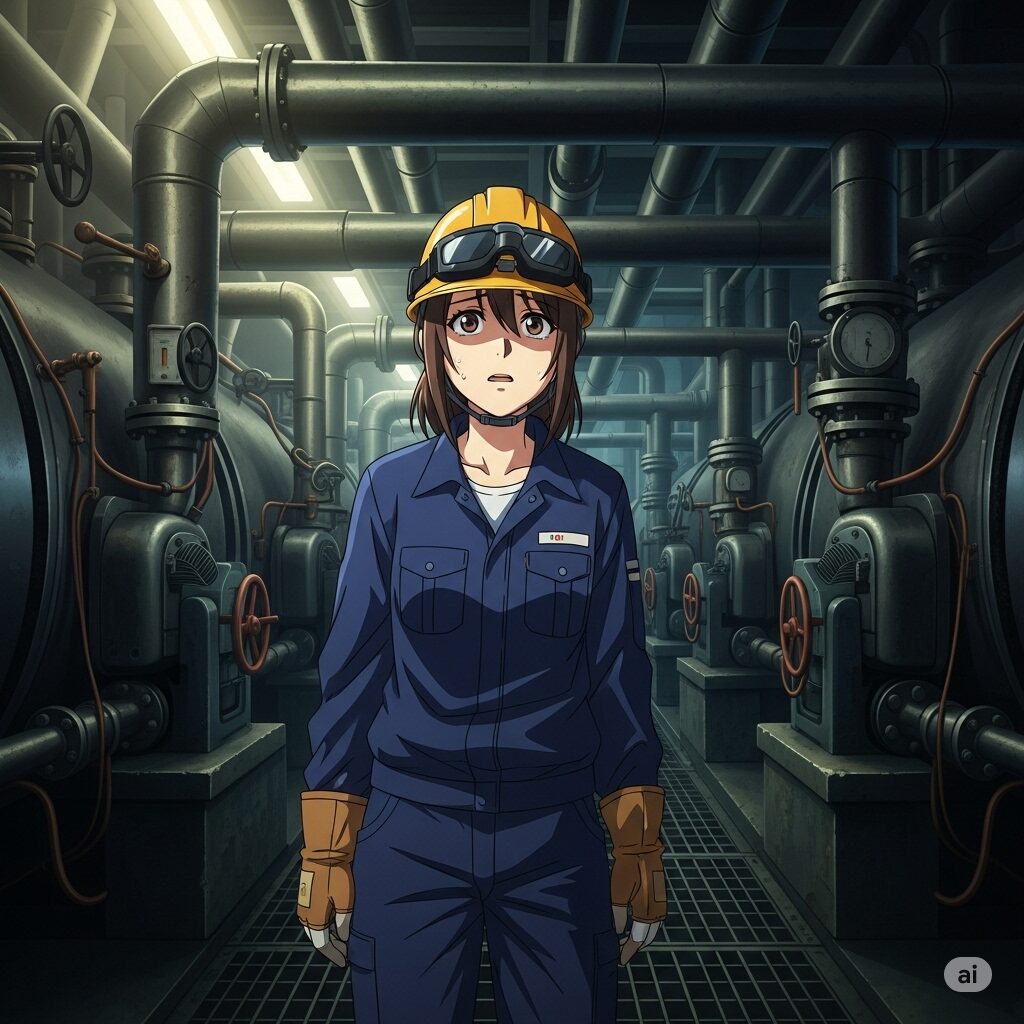
「ビルメンの仕事って楽そう」。そんなイメージで入社して、すぐに辞めていく若者を20年間で何人も見てきました。しかし、この業界には知られざる「闇」と、一方で確かな「光」も存在します。この記事では、なぜ多くの若者がビルメン業界から去ってしまうのか、その5つの具体的な理由をベテランの視点から正直に解説します。この記事を読めば、ビルメン業界のリアルな実態と、厳しい環境でも賢く生き抜くためのヒントがわかります。
- 給料が上がらない?業界の給与体系と絶望的なリアル
- キャリアパスの行き止まり感…資格を取っても明るい未来は描けないのか
- 不規則な宿直勤務と心身への負担「楽」とは程遠い現実
- 閉鎖的な人間関係と独特の「村社会」カルチャー
- 「誰でもできる仕事」という世間の目と失われていく誇り
1:給料が上がらない?業界の給与体系と絶望的なリアル
「ビルメンは給料が低い」とよく言われますが、問題は単に低いだけではありません。本当の絶望は「上がらない」ことにあるんです。私がこの業界に入った20年前から、給与水準はほとんど変わっていません。多くのビルメンテナンス会社は、建物のオーナーから委託を受けて業務を行いますが、その契約金は年間の入札で決まることがほとんど。コスト削減の圧力が常に働くため、従業員の給料に還元されにくい構造的な問題を抱えています。
若手は「経験を積めば」「資格を取れば」と期待しますが、現実は厳しい。第二種電気工事士や危険物取扱者などの「ビルメン4点セット」を取得しても、手当は数千円程度という会社もザラです。昇給は年に一度、雀の涙ほど。これでは、家庭を持つことや将来の生活設計を描くのは難しいでしょう。大手系列系の会社であれば多少はマシですが、多くの独立系ビルメン会社では、これが現実なのです。
2:キャリアパスの行き止まり感…資格を取っても明るい未来は描けないのか
「資格を取ればキャリアアップできる」というのは、半分本当で半分嘘です。確かに、電験三種(第三種電気主任技術者)やビル管(建築物環境衛生管理技術者)といった難関資格を取得すれば、選任者として責任ある立場に就け、給与も上がります。しかし、そのポストには限りがある。一つのビルに何人も責任者はいりませんからね。
多くの社員は、現場のいち担当者としてキャリアを終えます。現場のリーダー(主任)になったとしても、その先は所長、エリアマネージャーと続きますが、これもまた狭き門。結局、何年経っても同じような点検や簡単な修繕作業の繰り返し。「俺は何のために頑張っているんだろう」と、キャリアの行き止まりを感じて辞めていく若手は後を絶ちません。技術を極めようにも、現場の設備は古く、新しい知識が活かせないというジレンマもあります。
3:不規則な宿直勤務と心身への負担「楽」とは程遠い現実
ビルメンの仕事には「宿直」や「夜勤」がつきものです。24時間、建物に何かあれば駆けつけなければならないため、これは仕方のないこと。しかし、この不規則な勤務形態が心身に与える負担は、想像以上に大きいものです。「仮眠時間が長いから楽だ」と言う人もいますが、緊急対応で叩き起こされることも日常茶飯事。常に緊張感を強いられ、熟睡などできません。
日勤、夜勤、宿直とバラバラのシフトを繰り返すうちに、体内時計は狂い、自律神経のバランスを崩す人も少なくありません。友人や家族との時間も合わなくなり、社会から孤立しているような感覚に陥ることも。体力的にタフなだけでなく、精神的な強さも求められる。「待機時間が多くて楽」というイメージだけで入ってくると、このギャップに苦しむことになります。
4:閉鎖的な人間関係と独特の「村社会」カルチャー
ビルメンテナンスの現場は、基本的に少人数で固定されたメンバーで働くことが多いです。そのため、一度人間関係がこじれると逃げ場がありません。まさに「村社会」。現場の責任者や古参の先輩が絶対的な権力を持っていることも多く、新しい意見や改善提案が受け入れられにくい風潮が根強く残っています。
「昔からこうだから」「余計なことはするな」。そんな言葉で、若手のやる気やアイデアの芽が摘まれていく光景を何度も見てきました。テナントやオーナーとの板挟みになることも多く、コミュニケーション能力も求められますが、社内の風通しが悪ければ、ストレスは溜まる一方です。この閉鎖的な環境に耐えきれず、もっと風通しの良い職場を求めて去っていくのです。
5:「誰でもできる仕事」という世間の目と失われていく誇り
これが、ベテランとして一番悲しく、そして根深い問題かもしれません。ビルメンの仕事は、建物の安全と快適を支える、社会にとって不可欠な仕事です。電気、空調、給排水、消防設備…どれか一つでも欠ければ、多くの人々の生活や仕事に支障が出ます。しかし、世間からの評価は「ビルの管理人さん」「楽な仕事」といった程度。専門性や仕事の重要性が正しく理解されていないのが現実です。
トラブルがなくて当たり前。感謝されることも少なく、何か問題が起きた時だけ矢面に立たされる。そんな毎日の中で、自分の仕事に対する誇りを見失ってしまう若者は少なくありません。「もっと人から感謝される仕事がしたい」「自分のスキルを正当に評価してくれる場所で働きたい」。そう考えて、別の業界へ転職していくのです。この仕事の本当の価値を、私たち自身がもっと発信していく必要があるのかもしれません。
あとがき
ここまでビルメン業界の厳しい現実についてお話ししてきましたが、決して「辞めるべきだ」と言いたいわけではありません。この仕事には、建物を裏から支えるという大きなやりがいがあり、一度身につけた技術や知識は一生モノです。大切なのは、業界のリアルを知った上で、自分なりの目標や働き方を見つけること。この記事が、これからビルメン業界を目指す方、そして今まさに悩んでいる方の、一つの道しるべとなれば幸いです。







